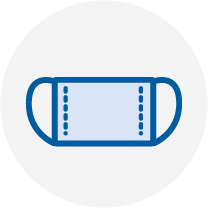フィットクリニックでは、EDや早漏、AGA・FAGA、緊急避妊、禁煙、ダイエット、ニキビなど、様々なお悩みに幅広く対応しています。
このページでは、フィットクリニックで治療している症状・お悩みを一覧でご紹介します。
以下の中から気になる症状・お悩みをお選びいただくと、考えられる原因や治療法などを解説した記事一覧をご覧いただけます。
EDの症状・悩み一覧
満足な性行為を行うために十分な勃起が得られない、または維持できないという症状に悩む方は、ED(勃起不全)の可能性があります。
以下は、EDの症状や原因などをわかりやすく解説している記事一覧です。
早漏の症状・悩み一覧
早漏(そうろう)とは射精障害の一種で、男性が性行為中に自分の意図する時間より早く射精してしまう状態を指します。
以下の記事では早漏の症状・原因を解説しています。
- まずはこちらの記事がおすすめ
- 早漏の原因と治し方
- 射精障害の原因と治し方
AGA(男性の薄毛)の
症状・悩み一覧
AGAとは「男性型脱毛症」のことで、額の生え際や頭頂部を中心に髪が細く抜けやすくなるなどの症状があります。
以下の記事ではAGAの症状や特徴、原因などを詳しく解説しています。
- まずはこちらの記事がおすすめ
- AGA(男性型脱毛症)の症状や特徴
- AGAの原因
- AGAの原因と治し方
- AGAと遺伝の関係性
- AGAの予防
- AGAの予防方法
- AGA予防に効果的な食べ物
- 症状別の男性の薄毛
- つむじ(てっぺん)はげ
- 若ハゲ
- 円形脱毛症
- 脂漏性脱毛症
FAGA(女性の薄毛)の
症状・悩み一覧
FAGAとは女性特有の薄毛や脱毛症を指します。
以下の記事では、FAGAの症状の特徴や原因を詳しく解説しています。
- まずはこちらの記事がおすすめ
- FAGA(女性の薄毛)の症状や原因
- びまん性脱毛症の症状や原因
- 症状別の女性の薄毛
- こめかみハゲ
- 休止期脱毛症
- 牽引性脱毛症
- 産後脱毛症
- 年代別の女性の薄毛
- 20代女性の薄毛になる原因と対策
- 更年期症状が原因の抜け毛の原因と対策
避妊の悩み一覧
予期せぬ妊娠や避妊失敗のリスクは、性行為の状況や方法によって変わります。
正しい避妊方法やトラブル時の対処法を知り、安心して対策できるようにしましょう。
- まずはこちらの記事がおすすめ
- 避妊方法と種類
- 避妊と妊娠のリスク
- 生理1週間前の妊娠の可能性
- 膣内射精(中出し)の妊娠確率
- 膣外射精(外出し)の妊娠確率
- コンドームが破れた場合の対処法
- 避妊と性被害への対応
- レイプされた場合の妊娠被害対応
ニコチン依存症や禁煙の
悩み一覧
喫煙をやめたいと思っても、ニコチン依存症や離脱症状に悩まされる人は少なくありません。
以下記事では、男女別の禁煙のポイントや、喫煙による健康・美容への影響、受動喫煙のリスクなどを詳しく紹介しています。
- まずはこちらの記事がおすすめ
- ニコチン依存症と禁煙方法
- 禁煙の離脱症状
- 男女別の禁煙について
- 男性が禁煙するメリット
- 女性の禁煙による効果
- 喫煙のデメリット
- タバコによる歯の黄ばみ
- 喫煙者の肺・肺がんのリスク
- 受動喫煙のリスク
- その他
- 禁煙治療の保険適用
ダイエットの悩み一覧
体型や体重が気になる人は、部位や年代などによって原因が異なります。
以下記事では効率的なダイエット方法や停滞期の対処法などをご紹介していますので、ご自身の悩みに合った改善策を見つけましょう。
- まずはこちらの記事がおすすめ
- 太る原因と痩せる方法
- 状況別の原因
- 中年太りの原因
- 下半身太りの原因
- お腹だけ太る原因と痩せる方法
- 状況別・部位別ダイエット
- 女性のダイエット
- 産後ダイエットにおすすめの運動
- 更年期のダイエット
- ダイエットの停滞期
- 皮下脂肪を落とす方法
- 年代別ダイエット
- 30代のダイエット法
- 40代のダイエット法
- 50代のダイエット法
- ダイエットと食事
- ダイエット中の痩せる食事法
- 簡単ダイエットレシピ
- その他
- メディカルダイエットの保険適用
- 肥満・肥満症のリスク
- 痩せるツボ
- ダイエットと腸内環境の関係
- 朝昼夜のダイエットルーティン
ニキビの症状・悩み一覧
ニキビは部位や肌質によって原因や症状が異なり、思春期・大人・部位別で悩み方も変わります。
種類ごとの特徴やケア方法を知り、悪化を防ぎながら改善しましょう。
- まずはこちらの記事がおすすめ
- ニキビの症状と原因
- ニキビの予防
- ニキビの予防方法
- ニキビの場所別
- ニキビの場所別の原因と対策
- 首ニキビ
- ニキビダニ(顔ダニ)とは
- 鼻ニキビ
- 鼻の下(人中)ニキビ
- ニキビの種類
- ニキビの種類と症状
- 赤ニキビ
- 黄ニキビ
- 紫ニキビ
- 大人ニキビ
- その他
- 酒さ(しゅさ)の原因と治し方
インフルエンザの症状・悩み一覧
インフルエンザは感染後の治療よりも、感染を防ぐことが大事です。
インフルエンザの症状や特徴、対処法について知り、適切に対策をしていきましょう。
- まずはこちらの記事がおすすめ
- インフルエンザとは
- インフルエンザの感染率
- インフルエンザで休む期間
花粉症の症状・悩み一覧
現在、花粉症によるくしゃみ・鼻水・鼻づまり、目のかゆみなどの症状でお悩みの方は少なくありません。<> 以下のページでは、症状や特徴、症状の出る前からできる対処法、改善方法などを確認いただけます。
フィットクリニックでは、ED・早漏・AGA・FAGA・禁煙治療・メディカルダイエット・ニキビ治療・インフルエンザのオンライン診療を行っています。
アフターピルの処方は外来のみとなりますので、来院での受診をお願いいたします。
何かお悩みがある場合は、当院へお気軽にご相談ください。
各処方薬の紹介や当院について詳しくは以下をご覧ください。